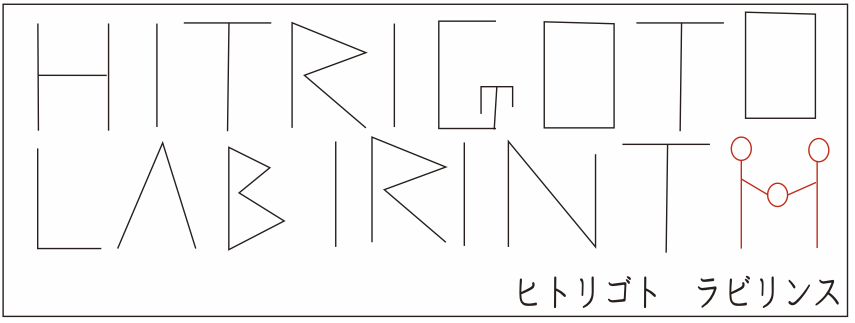昔書いた映画レビューの詰め合わせ
メモアプリに眠ってて懐かしかったので久々の更新
『ミリオンダラー・ベイビー』 クリント・イーストウッド監督作
『ミリオンダラー・ベイビー』第77回米国アカデミー賞では、作品賞を含む7部者を受賞し、イーストウッドの監督としての評価を確固たるものにした。
本作は、さまざまな角度から議論が必要な題材を扱い。その扱い方についても本国では賛否両論を噴出している。ゆえに思想・描写という点においては評価が難しい作品とも言える。
だが、映画的演出という意味において。イーストウッドの円熟した技が見られる作品なのは間違いない。
貧困に喘ぎながらも、なんとか入校費を払い。がフランキー(クリント・イーストウッド)経営するボクシングジムに出入りするマギー(ヒラリー・スワンク)。年老いて諦観を覚え、人とのつながりを恐れるフランキー。彼は最初、マギーを遠ざけようとするものの、自身と同じような境遇あるマギーにだんだんと肩入れしていく。傷を抱えながらも、距離を詰めていく二人。それと比例するように腕を上げるマギーは、だんだんと試合でも勝ち進んでいく。
ここだけ見ると、正統派のサクセスストーリーに見える。だが、画面にも現れているように『ミリオンダラー・ベイビー』は影の映画だ。マギーとフランキーの二人が楽しげに会話しているシーンでも、絶えず二人の顔には影がかかり続けている。これから彼らが歩む壮絶な道のりは、実は前々から暗示されているのだ。
本作が『ロッキー』ではなく『キッズ・リターン』だったということが分かってくるのは中盤以降だ。お互いが掴みかけた理想は、手の中からこぼれ落ちる。この映画は「後味が悪い作品」と評されることが多いが、その要因はここにあるのではないかと思う。だが、イーストウッドはその絶望すらも、ものすごく引いた目線で切り取る。
序盤から、題材に比べて冷めたトーンで切り取られた二人の友情だが。その引いた目線が、ハードボイルドを体現してきたイーストウッドの目線なのだろう。だからこそ、本作は映画としてとても洗練された熟練の技が光る。
光と影の演出、小さな仕草で感情を見せる上手さ。それが結実するのが、映画のラストだ。
中盤出てきた「あの店」をこんな形でリフレインさせるその感動と哀しさは、本作をただの「後味の悪い映画」とまとめさせないパワーを映画に与えている。イーストウッドがこれまで撮ってきた、継承と死に場所の映画としても。歴史に残る傑作だ。
『君たちはどう生きるか』宮崎駿監督作
宮崎駿は、きっとこの作品で自分を語ったのだろう。自身の過去作、自身が影響を受けてきた作品の要素をとにかく取り入れて。自身の箱庭を映画の中に作り上げた。だからこそ、本作は一義的な解釈を否定する。
前作『風立ちぬ』は逆に、かなり一義的な解釈がしやすい作品だったと私は思っている。アーティスチックな作家性を発揮しているので分かり辛いが、宮崎駿という作家を真ん中に置いた時に「こうみて欲しい」という意図は分かりやすい作品だったと思うのだ。
ストーリー自体は古典的自動文学を踏襲している『君たちはどう生きるか』がそれでも難解と言われる原因は、「こう見て欲しい」という解釈を作品がはなから投げているところにあると思う。例えば主人公の直人は、宮崎駿の幼少期と読み取る解釈が主流だ。だが個人的には、観客のメタファーという読み解きも可能だと思う。宮崎の兄という読み解きをしている人もいた。このように多分に読み解き可能なメタファーとして、すべての要素が置かれている。例えば父親のキャラも、宮崎の父親であると同時に、父親としての自分自身を重ねているようにも感じた。
そんな解釈可能な要素の羅列で構成されていると言っても過言ではない本作だが。だからこそ、本作は頭をフル回転させて作品から何かを受け取ろうとする者だけに門戸を開く。芯の髄から「アート映画」なのだろう。
そして、アート映画的な作りは。改めてエンターテイメント作家・宮崎駿の魂を再生させたようにも感じる。もともと宮崎は、ウェルメイドな作家では決してない。作画技術とスペクタクルの見せ方で、「すごいもの見れた」をゴリ押しするタイプの作家だったはずだ。アート映画的な作りを選択して、要素の羅列に意識を振ったことで。むしろ宮崎アニメーション原初の快感のようなものが全面に出た一作となっているのだ。本作を見て「作風が若返っている」と感じた人も多いだろうが、それはこう言った要素も関係している。
私は『風立ちぬ』を傑作だと思いつつも、少し不満がある。宮崎駿の分身となる吾郎は、最初から最後までイノセントな存在として置かれ、それは宮崎の実態とは乖離したもの見えたからだ(宮崎はもっとアニメを作ることに対して清濁併せ飲んでいる印象がある)。対して『君たちはどう生きるか』は宮崎の今の姿が、メタ的にも作品内にも克明に浮かびあがる。彼らしさ全開になった一作で、宮崎駿の現在地を示す一作でもある。
『ビリー・リン永遠の一日』 アン・リー監督作
『ビリー・リン永遠の一日』は、日本劇場未公開作品となってしまった。これは惜しい…劇場鑑賞にこそ意義がある作品だと言わざるを得ないからだ。
それは本作の成り立ちを見てもわかる。アン・リー監督は最新の映像技術を映画内で上手く使うことに長けた監督だ。本作もそんな監督の映像的実験が込められた作品で、120FPS・4Kデジタルでの撮影が敢行された一作なのだ。
つまり、映像を細部まで堪能できる映画館で見てこそその真価が発揮されるタイプの作品で。これがビデオスルーとなったのは、本当に惜しむべきことだ。
だが、こう聞くと『ビリーリン永遠の一日』は映像技術の習作映画なのではないかと思う人もいるかもしれない。しかし、そうではない。今作が最新鋭の映像技術でもって描き出すのは。一人の兵士の「個」のドラマだ。
本作における映像技術は、あくまで主人公が体験した戦場のリアルを、ソリッドに写し出すためのものであって。本筋となる兵士のドラマは、むしろ文学的だ。
仲間の兵士を助けるべく弾丸の中を駆ける主人公ビリー・リン。それが報道された途端彼は英雄として迎えられる。しかし、彼が体験した「現実」はそのイメージからは乖離したものだった。
アン・リー監督は自作のテーマを一貫して「イノセンスの喪失である」と語っている。今作も、ビリー・リンが戦場の体験を通して、純粋さを喪失していく話だ。ゆえに、今作の戦場描写はグロテスクに作り込まない。その冷めた感覚が、逆に観客の心を抉る。
戦場から戻った兵士は、もうアメリカの一般的な日常に戻ることができない。「イノセンスを喪失」し世界から拒絶されたビリー・リンを理解してくれるのは。同じ体験をした仲間の兵士たちだ。本作はビリー・リンが理解者を見つけると同時に、もう戻れないところまで行ってしまった状態を描いて終わる。それはどう受け止めていいのかわからない、とても複雑な余韻を残す。
120FPS、4Kという映像的挑戦は。あくまでこのテーマに説得力を持たせるためのものだ。この作品がヒットしない理由もわかる。映像技術に力を入れているわりに、テーマも描き方もあまりにもハイコンテクスト。主人公の目線に寄り添った撮影はスペクタクル性も皆無だ。でも、だからこそ生まれる余韻と哀愁は。映画史に残るものだと私は思っている。
願わくば、映画館での上映を。いつか…。
『偶然と想像』 濱口竜介監督作品
本作は、短編が3本立になっているオムニバス映画となっている。それぞれの間に連続性はない、だがこの3本がこの順番であることには、強い意味がある。ストーリーに連続性はなくても、映画を見る感情は連続している。それぞれのストーリーを見終わったあと残るエモーションの連続が、映画に独特の後味を残している。
本作のテーマは、実にシンプル。それは「後悔」だ。特に私が刺さった『魔法(よりもっと不確か)』では、そのテーマが全面展開されている。
会話の中で、友人が元カレに惹かれていることに気づいた主人公が。久々に元カレに会いに行き、「あの頃の関係」について議論するというストーリー。『ドライブ・マイ・カー』でも描かれたような、喪失に蓋をした結果拗れてしまった男女が描かれる。過去というのは、変え難い割には思いを馳せやすいように出来ていて。『魔法(よりもっと不確か)』はそのファンタジーに思いを寄せてしまう感情を強く抉る。だが、時間は戻らない。ドロドロとした後悔で蓋をしてしまった主人公の本音は「まだ彼が好き」というシンプルで純粋な物だった。だが、もう時は進み、関係性は大きく変わってしまっている。もう昔のようには戻れない。真にそう突きつけられた時、彼女は顔を抑え涙する。
『魔法(よりももっと不確か)』『扉は開けたままで』がそれぞれ切ない幕切れを迎える分、トリを飾る『もう一度』は、温かく希望に満ちた作品になっている。前半2作品では、それぞれ抱えた後悔の本質に直面し、それを自覚するまでのストーリーゆえに、結末は哀しいものになりがちだった。だが『もう一度』では、一貫したテーマとなっている「後悔」が回収され、解消されていく様子をこそ描く。その回収というのが、本作のもう一つのテーマになっている「演技」だ。『魔法(よりももっと不確か)』でも『扉は開けたままで』でも、主人公たちは自分自身を演じている。だからこそ、本音をぶつけ合い感情に折り合いをつけるシーンほど抽象的な演技によって語られるのだ。『もう一度』では、「あの時」の状況を二人で演じ直すことで。後悔が昇華されていく。観客も前2作で溜まっていたフラストレーションが回収されることで、大きな感動が生まれるわけだ。
『若おかみは小学生』高坂希太郎監督作品
新海誠監督の『すずめの戸締り』は、喪失と向き合い、受け入れるまでの物語だった。喪失と向き合い、受け入れる物語は。日本アニメの傑作を生み出し続けている。『若おかみは小学生』もその一つだ。
ジャンルとしては児童向けアニメという装いで、「見なくても大丈夫だろう」と敬遠してしまった人も多いのではないだろうか。だが、本作はものすごくハードな喪失のドラマを描いている。
まず、監督の高坂希太郎という人物を解説しておこう。高坂は、長くジブリの作画監督として活躍してきた人物だ。有名なのは『風立ちぬ』などであろうか?そんな高坂だが、演出家としても高い力を持つ。監督を務めた『茄子 アンダルシアの夏』『茄子 スーツケースの渡り鳥』の2本では、自転車レースとそこに全てをかける男のドラマを描き。作画面、ドラマ面両方での高い評価を得た。
だから『茄子』シリーズに続く監督作が『若おかみは小学生』だと聞いた時は、正直驚いた。『若おかみは小学生』は青い鳥文庫で発刊された児童文学シリーズで、子ども向け色が強い印象がある。『茄子』シリーズの印象が強かった私は、どんな方向性になるのだろうとワクワクしながら公開を待ったのを覚えている。
結論から言うと映画『若おかみは小学生』は傑作だ。本作の前に、10分アニメとして制作されたTVアニメシリーズがあるが。こちらは未見でも全く問題ない、本作はこのTVアニメシリーズの続編や姉妹編ではなく。同じ原作の調理法を変えたものという立ち位置が正しい。
では、映画版の「調理法」とはなんだったのか?それは、原作が持っていた抽象的なモチーフをある程度リアルに解釈し直すと言うことだ。「自動車事故で両親を亡くした主人公」「未練を抱えて出てくる幽霊」といったモチーフのシリアスさを上げて描く。だが作品全体のバランスとしては、子ども向け作品となっているので独特のバランスの映画になっている。
この映画は主人公おっこが喪失と向き合う様子を丁寧に描く。基本的には明るい作風だが、その明るさがおっこの危うさを逆に浮かび上がらせる。おっこはよく、両親と一緒にいる夢を見るのだが。これが現実とシームレスに接続されるというのも、その演出の一環だ。そんな危うさを抱えたおっこが。出会いを通して他者と向き合い、自分の心を他者に開いていく。子ども向けと思いきや、心に刺さり響く、大人も感動できる傑作だ。
『サイン』 M・ナイト・シャマラン監督作品
『シックス・センス』で映画監督としての名声を確固たるものにしたシャマランだが。『シックスセンス』も改めて見返すと穏当な映画とは全く言い難い、良い意味で歪な構成の映画である。ブルース・ウィリス演じる警官と幽霊が見える少年との心温まる交流の映画かと思いきや。そこにはホラー的演出含め、明らかにバランスを欠いた演出が頻出するわけだ。もちろんこれが意図して崩されたバランスであることは、その後作られた映画である『サイン』を見るとよく分かる。
『サイン』はストーリーについての映画だ。メタ映画と言っても良い。作家の伊藤計劃はデビッド・フィンチャーの『セブン』を「フィンチャーはドラマやサイコ・スリラーなどという、チマチマした人間感情をものを撮る監督ではなく、極めてポストモダン的に映画を撮る、メタフィクション作家であるといえます」と評したが、これはシャマランにも当てはまる。
だが、フィンチャーが少なくとも映画内ではそのジャンルに奉仕した語り口をとるのに対し。シャマランは映画内でも「ポストモダン的なメタフィクション作家」であるスタンスを強く主張する。例えば、映画『オールド』でシャマランは主人公家族を映画の舞台となる海岸に連れて行き、それを観察するという役を自ら演じている。これは自身が映画内の理を糸引くデウス・エクス・マキナであるということに自覚的な証拠ではないだろうか。シャマランはいつだって物語を超観する視点を自覚的に映画内に置く。
そんなシャマラン的作家性の集大成が、今作『サイン』だ。まず、普通の映画だと思って鑑賞すると間違いなく面食らう。映画における「オーソドックス」な語り口からはかなり乖離した作品だからだ。というか、見始めてしばらく経っても映画のジャンルが分からない。とうもろこし畑にできたミステリーサークルの正体を調べようとする一人の男が、今作の主人公だ。それぞれ何かを諦めたということが提示される主人公家族たち。ミステリーサークルというSF設定に比べて、その喪失をこそ丹念に描くバランスに。観客は少なくない困惑を覚える。だが、その困惑もシャマランの掌の上だ。
ラスト、映画全体の構造が回収されていく。『シックス・センス』のウェルメイドなドンデン返しとは全く違った、ある意味強引でご都合主義とも思える話運びは。シャマラン的テーゼを強く意識させる。それは「超越的な物からの導き」だ。映画芸術において「ストーリー」によって登場人物が動かされるということに意識的なシャマランの作劇は、ひいては神の存在のような物すら作品内に意識させる。もちろん、その神の正体は監督であるシャマラン自身だ。
『アマデウス』 ミロス・フォアマン監督作
本作は『天才』とその才能に恋焦がれた人間の話だ。宮廷音楽家であるサリエリが天才音楽家ヴォルフガング・アマデウス・モーツアルトに嫉妬し続けた半生を振り返る。
サリエリの悲劇は、モーツァルトの才能を理解できてしまったところだろう。『アマデウス』には多数の宮廷音楽家が登場するが、その大半はモーツアルトの自堕落な私生活と破天荒な音楽性から、彼を評価しない。だがサリエリは違う。彼は音楽家として才能があったが故に、モーツアルトを正しく評価できてしまったのだ。
しかし、本当の悲劇は才能を理解できたことではなく。才能に焦がれてしまったことではないかと、私は思う。その瞬間に、人は逃れようのない絶望の業を負うことになる。私は劇作家、中屋敷法仁が書いた『贋作マクベス』のセリフを思い出した。この作品では、マクベスが苦悩する理由を「自己満足できなかったからだ」と看過する。サリエリも同じだ。モーツアルトという届かない天才に焦がれた時点で、「自己満足できる瞬間」はもう来ない。どんな傑作を作り上げたとて、「自身の中にあるモーツアルト」を超えることはできない。それは決して到達できない理想の音楽が、形をとって表れたものに他ならないからだ。(それは「神」という存在のメタファーとも思える。本作はキリスト教的なモチーフが至るところに散りばめられた作品なのだが、サリエリとモーツアルトの関係を通して、神と人間の在り方を描き出そうともしているということだろう。)
その葛藤はSNSによって才能が比較されやすい現代のほうが普遍的になったのではないだろうか。
そんな葛藤に対して映画が出す結論は。とても優しい。サリエリはこの映画ラストで「凡才の凱旋」を語る。そのシーンは、これまで室内劇が中心だった『アマデウス』において。初めてしっかりと外の世界が描かれる瞬間でもあるが「神」の前に苦悩して悩む存在だったサリエリは、転じて凡人を許す側へとその立場を変える。
つまり『アマデウス』は高潔で完璧な「神」の存在では救われなかった凡人たちのための映画なのだ。天才で破天荒なモーツアルトよりも、非才に悩み続けたサリエリの存在で救われた人は多かったのではないだろうか。
ちなみに、現実のサリエリは、映画で描かれたようなモーツアルトに固執し続けた人物ではなく。後進の育成に力を入れ、モーツアルトに勝るとも劣らない名曲を多々書いてきた人格者だったそうだ。もちろんそういった面を理解した上で見る必要がある映画でもある。
だが、「悪には悪の救世主が必要」だったように。凡人には凡人の救世主が必要なのだ。ミロス・フォアマンはサリエリという存在を使って、凡人のための神を作り上げた。
『aftersun/アフターサン』 シャーロット・ヴェルズ監督作
少女から見て父親はどういう存在だったろう?父親から見て少女はどういう存在だったろう?
『アフターサン』はそういう映画だ。31才となった娘の視点から、11才の時ビーチで父と過ごした思い出を「再生」する。大人になった視点から過去を回想する映画は『ニュー・シネマ・パラダイス』や『きっと、うまくいく』など数多く作られてきただろう。
『アフターサン』がそういった映画と大きく異なるのは、作中において「現代から過去を俯瞰している」という視点がラストになるまでほとんど登場しないことだ。いや、厳密に言えばそういった視点は存在する、この映画自体が「俯瞰視点」なのだ。
この映画は主人公の少女ソフィが撮影した、もしくはされた動画を視聴しているという形式で進行する。だが、明らかにカメラが切られている状況が映像として現れている点からもわかるように。その映像を見て想起される少女の記憶が映画化されているものと見るべきだろう。
だが、それではおかしい。この映画では当時娘が知り得なかったはずである父親の視点も映画として存在する。これこそがこの映画における『俯瞰視点』つまり、現代のソフィが以降に体験した出来事から想像できる「父親の視点」を自身の記憶の中に作り上げたのだ。
そういった視点で見ると、父親、カラムの行動には危うげな点が多い。フェンスの上に立つ、鏡に唾を吹きかけるといった行動をとる。決定的となるのは夜の海に消えてゆくシーンだろう。カラムが海に消えていってからも、スクリーンはその海を写し続ける。波の音はさらに大きくなって、カットが変わるまでうるさいほど大きくなり続ける。少し恐怖すら感じるようなシーンだった。
カラムはソフィの前では非の打ちどころのない良い父親に見える。だからこそ特に映画終盤、ソフィが当時体験した事象とカラムの視点を分けて考えると、間接的に「今」のカラムとソフィがどういう状況にあるか浮かび上がってくる。『aftersun』の意味は日焼けあと。これほどまでに秀逸なタイトルはないだろう。あの日が燦々と照りしきる夏の思い出はもう終わり、その記憶は日焼け跡のヒリヒリとした痛みから思い出すしかない。
少し構造が複雑で、初見では魅力が伝わりずらいところもあるかもしれない。私も正直面食らった部分はある。
だがこれだけの複雑な構造を、完璧なカメラワークで映画という形にしてしまった監督のシャーロット・ヴェルズは。なんとこの『aftersun/アフターサン』が長編監督第一作なのだ!まずはこんな天才的な作品を撮る監督と同じ時代を生き、一作目から作品を追えることを寿ぎたい。
『そして僕は、途方に暮れる』三浦大輔監督作
監督は『何者』『ボーイズオンザラン』等で知られる三浦大輔。主演は、Kis-My-Ft2のメンバーでもある藤ヶ谷太輔。
元ジャニーズ(現:SMILE-UP)の藤ヶ谷が主演を務めてこそいますが、この映画自体はダメ男のダメさを描くコメディー。本当に、主演の藤ヶ谷さんがそういう男にしか見えない感じで体現する、主体性のないダメ男。
そのダメさゆえに、彼はその場から逃げる行為を繰り返す。同棲中の彼女から浮気を疑われれば言い訳して逃げ、友達の家に転がり込んだと思えば、そこでも痛いところ突かれて逃げる。そんな風に逃げ続ける彼のダメさを見て笑いながらも身につまされるダーク・コメディ。
個人的には、そんな彼のダメさを見て。救われた部分も大きかったです。彼は躊躇いなくダメであってくれるというか…。自分自身のダメさをお焚き上げしてくれる部分もあったので。
だけど、何よりこの映画で描き出されるのは「残念なシネフィル」の姿でもあるんですよね…。
主人公が映画ファンである(あった)のは、さまざまなところから伺い知ることができます。冒頭映し出される、映画雑誌を処分しようとしているところや、先輩の家に転がり込んだ際の会話から「映画を撮ったことがある」ということもなんとなくわかります。
彼はある意味「夢に呪われている」男です。だから映画業界に就職した後輩に、超上から目線で悪態をついたりもするわけです。(恥ずかしながら、気持ちは少し分かります)そんな彼が、再起していく話でもあるというのが、本作ラストの感動にも繋がってくるのだと思います。
この映画で印象に残るシーンは、なんといってもラストシーンでしょう。序盤と対になった「家を出るという」行動から、歩く道は東京の映画ファンにはお馴染みの「あの道」。三浦監督はいつも「自分中心のセカイ」が崩壊する瞬間をこそラストに映し撮ります。でも、そこにあるのは単に絶望のみではないのです。
観客は序盤、彼のダメダメ具合を笑っていた時には想像もつかなかったような複雑な感情で映画館を後にすることになります。主人公はとても大きな「成長」をしたわけではありません。でも、だからこそ彼の等身大の逃避行の結末は、彼が初めて自分で掴み取った「現実」でした。笑えて、そして少し哀しき逃避行。そのいく末は、地獄か天国か。
『AIR/エア』 ベン・アフレック監督作
何よりこの作品に惹かれた理由は、その志にある。
「アーティスト・エクイティ」。ベン・アフレックとマット・デイモンという名優二人が共同で立ち上げた会社だ。今作『AIR』の制作および製作は、監督も務めるアフレックが設立したこの会社が務めることとなる。デイモン曰く「先見性のあるクリエイターが自らのビジョンを形にする場」として設立されたアーティスト・エクイティだが、その第一作として見ると『AIR/エア』はとても重厚な作品となっている。
本作は伝説のバスケ・シューズ、エア・ジョーダンの開発秘話を描く。主演は前述したマッド・デイモン、ナイキの重役、ソニー・ヴァッカロを破天荒に体現する。
何より目を引くのは、そのストーリーの語り口だ。本作を見ると感じると思うが、非常に80年代的な空気感が作品の中に充満している。テンポ感、音楽、出演キャスト。どれを取っても80年代に作られたような質感だ。アフレックとデイモンが自身の生きてきた、一番好きな映画史を体現してみせたということだろう。
80年代的な語り口で80年代のストーリーを語るという。ともすれば懐古主義ともなりかねない今作だが。映画を見ればわかるように、決してそれだけではない。現代を見据えた視点が、この映画にはある。
それは作品内におけるエア・ジョーダンの開発秘話が「現代における映画作り」の寓話になっている点だ。作中のヴァッカロは、封建的な上司陣に対して破天荒なやり方で勝利していく。それはまさにアーティスト・エクイティが映画界に及ぼした革命そのものとリンクする。特にマット・デイモンが映画ラストで、物語を語り継いでいくことの覚悟を語るシーン。マイケル・ジョーダンを説得するためのプレゼンではあるが、一つの物語論としても感涙を誘うシーンとなっているのだ。ここにこそ、アーティスト・エクイティにの覚悟を見て取れる。
そして『AIR/エア』はボックスオフィスでヒットを重ねた。アフレックとデイモンという二大スターが出演しているということが大きいだろうが。前述したように、ストレートに見えて覚悟や作家性が所狭しと詰め込まれた映画でもある(まさしくアーティスト・エクイティという会社の立ち位置を象徴するような)本作がヒットしたことで。映画内で語られたような、破天荒なクリエイティビティが市民権を得たという見方もできる。
快調な滑り出しを見せたアーティスト・エクイティの今後に、ぜひ注目して行きたい。
『RRR』 SSラージャマウリ監督作
『バーフバリ』シリーズの創始者S・Sラージャマウリ監督の最新作にして、間違いなく世界最高峰のアクション映画。それが今作『RRR』だ。
植民地時代のインドを舞台に、ラーマとビーム。二人の男が友情と使命の間で葛藤しながら、圧政に立ち向かうというストーリー。
今作の魅力は何と言っても、アクションの密度と情報量だ。「ド派手アクション映画」と聞くとどうしても、アクションだけが過剰に派手で、それだけが特出したバランスの悪い作品を想像してしまいがちだろう。しかし、本作は違う。アクションの派手さやけれん味は残しながらも、そのアクションに至るまでの動機や過程を克明に書き込み、エモーションの発露としてのアクションを作り上げているのだ。
何気ない日常シーンにすら、アクションの伏線が張り巡らされている。
例えば中盤に、踊り疲れたビームをラーマがおぶるシーンがある、単体で見ればやりとりも含めて微笑ましいシーンである。しかし、この「おぶる」という動作が終盤、アクションとして再び用いられるのだ。
このように、この映画の全てのアクションシーンは前のシーンを踏まえ構築され、それゆえに重厚さを持つようになっている。
しかしそれ以上に、そのアクションシーンが持つ熱が凄まじい。監督が「ヒロイックフレーム」と称するキメ絵がどのアクションにも絶対に用意されており。そのカットは絵画的、神話的な美しさすら讃えるようなものとなっている。アクション自体も荒唐無稽になりすぎず、しかしケレン味は失わない絶妙なバランスで構築されている。
私は『RRR』という作品を見て鑑賞して、真に面白いアクションを構築するためにはアクションシーンそのものを凝っていくのも大切だが、それ以上に、アクションシーンが他のシーンとどのような関係にあるか、どういった意味を持たせるのかを突き詰めていくべきなのだとすら感じた。
エバペロンもしくはエビータの棺
「聖女」は世を離れ、「政治」だけが残る
自分が持っている価値観や正義が、誰かにとって誘導されたものであるかもしれないという不安感を覚えました。まさにラストの群衆の一人は私かもしれません。
今だからこそ見たい作品です。
Megザモンスター2 短文感想
前作以上に「ジェイソン・ステイサムが主演のサメ映画」という事前情報から想像できる「こういうことが起きてほしい!」という欲求に応えきった快作です。
海洋アクションのみならず、脱出アクションや肉弾アクションと見せ場も豊富で観客を飽きさせません。
まさに「アメリカアクション大作」のツボを抑えた見やすくて楽しい映画ですが。脚本や見せ方など、実は随所に工夫も見られるところも素晴らしい。
笑って、泣けて、ハラハラできて、熱くなる。夏休み最後にふさわしい映画なのではないでしょうか。